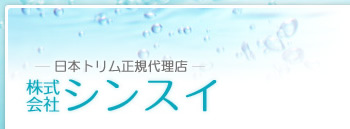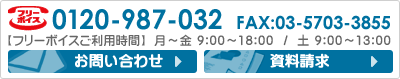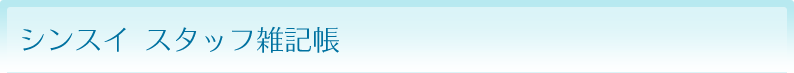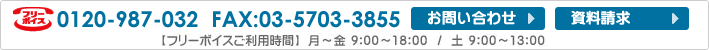久しぶりに、九州大学の白畑先生の講演を拝聴する機会に恵まれました。
カロリンスカ研究所との共同研究も、精力的に進めておられるようでした。
さて、講演を聴き終えて色々と考えさせられました。
抗酸化性を有する水といえば、
電解還元水や、水素ガスを溶存させた水素水が知られています。
何れも、今までは溶存している水素ガス(あるいは活性水素)が、
直接、活性酸素種を消去する「抗酸化剤」としての働きに
関心が寄せられていました。
ところが、近年は間接的に活性酸素を消去する働きが注目され、
水素はシグナル伝達因子として作用している可能性がある、と考える
研究者が多くなっています。
つまり、水素ガスは生体の抗酸化酵素(活性酸素を消去する)を誘導したり、
抗アポトーシスを誘導するなど、活性酸素除去だけではなく
他のシグナル伝達経路も制御しているというわけです。
水素ガスは拡散し、生体では微量しか取り込まれず残存性も高くはなさそうなので、
活性酸素を直接消去するには効率が悪いと考えても不思議ではありません。
そもそも、インビトロ(試験管)における水素ガスの活性酸素消去能は、
ほとんど期待できないという話です。
しかし、微量でも動物実験では酸化ストレスを抑制し、それなりの効果はみられる。
ところが、水素ガスは一定以上の濃度では増やしても効果に有意な差はみられない。
濃度依存的でもなさそうで、抗酸化剤としての働きは小さいのではないか?と考える
向きもあるのです。
水素がシグナル伝達因子として作用し、抗酸化酵素を誘導するなどして制御している
ということなのでしょうか?
しかしながら、水素ガスは生体内で腸内細菌の働きで大量に発生しているらしく、
なぜ、最初からこれを使わないの?という疑問もわいてきます。
それとも、使えない何らかの理由があるのでしょうか?
ところで、白畑先生は電解還元水には、活性水素(白金ナノ粒子に吸着)、
水素ガス、白金ナノ粒子(自身も抗酸化剤、触媒として働き水素分子を活性水素に)が
含まれており、還元水の効果についてはこれらの総合的な働きで説明されていました。
そうすると、水素ガスを溶存させた水と電解還元水では、
生理活性が微妙に異なるのでしょうか?
筋肉細胞への糖取り込みは、水素ガスだけよりも、水素ガス+白金ナノ粒子の方が
強く促進するらしいので、糖尿病の臨床では何か有意な差がみられるのかもしれません。
水で血糖値をコントロールできるなんて世間一般では信用されないでしょうから、
メーカーには、是非こういうところに積極的に取り組んで頂きたいですね。
今後、さらなる詳細な検討が行われることを期待します。
トップページへ
Home > シンスイ スタッフ雑記帳